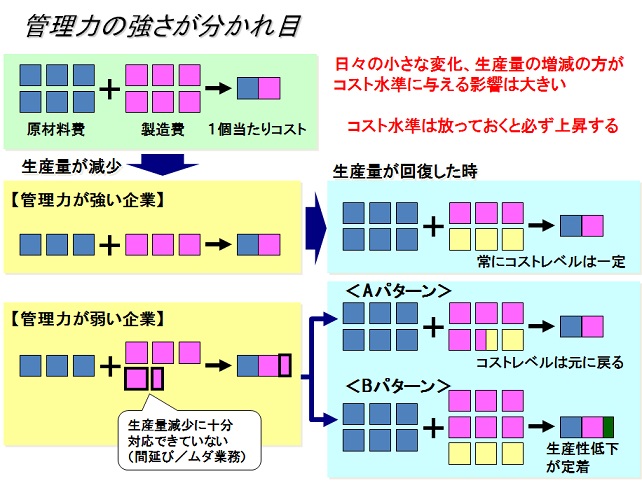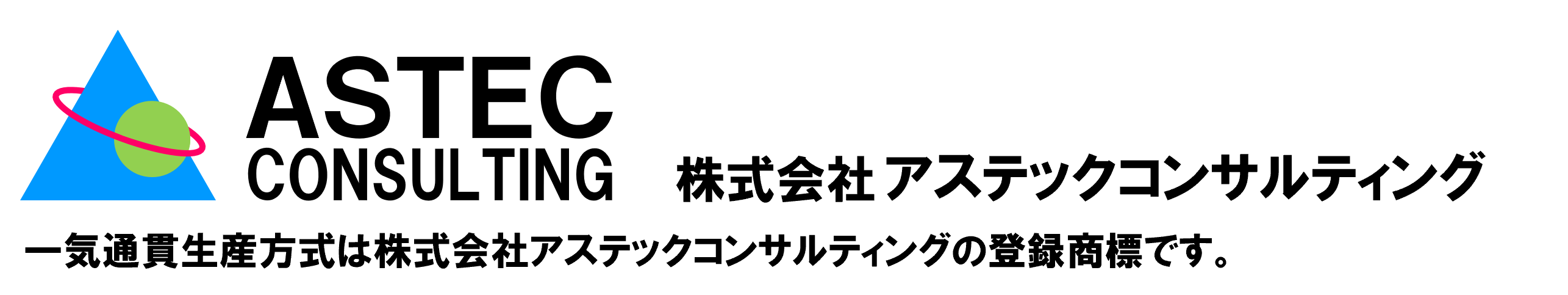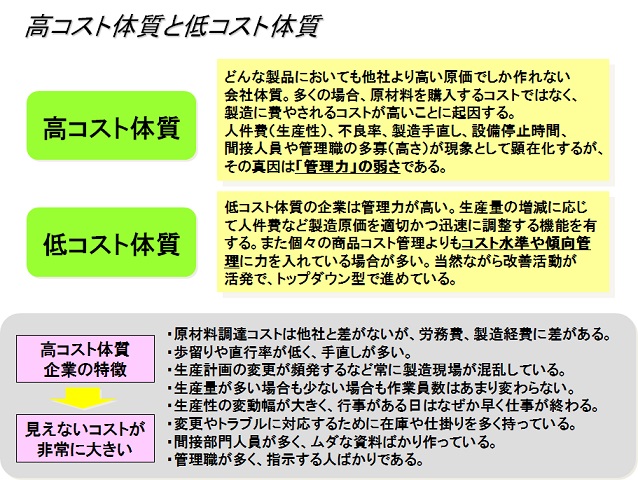前項では放っておくだけでコストが増大する話をしましたが、ここではコストの見える化により問題を抽出して改善活動をしたにも関わらず、成果がでないという事例を紹介していきます。
① 人件費低減のため労働生産性を指標として改善活動をし、+20%の生産性向上が確認できたが、労務費は全く変わっていなかった。
⇒整数単位の人員削減が出来ていないため。
たとえば0.4人分の工数を浮かせた場合は、その工数で別の付加価値作業をする仕組みを構築しないと作業が早く完了したが、その後、遊んでいる(ムダ)事になってしまう。
② 調達部隊が取引先別評価制度を導入してランク付け(見える化)を開始したが3年経ってもコスト低減は全く進んでいなかった。
⇒評価結果を実際の購入量に反映させる仕組みがないため。
コスト低減のための手段であるはずの取引先評価が目的となってしまい、評価するだけで終わっている。
③ ココスト見積をしたら内作より外注の方が低コストであることが判明し、外注出しを開始したが、製造コストはむしろ上昇してしまった。
⇒見積の数字を信じてしまっている失敗の典型例。
外注出しは社内工数が不足している場合には有効であるが、社内工数(=固定支出)が余っている状況で外注出し(外部流出費発生)を推進すれば、コスト上昇は当然。
④ 海外メーカーの部品がコスト見積の結果、自社部品に比べ30%も安いため早速導入し、部品購入費は大幅に低下したが利益は横ばいのままであった。
⇒コスト見積はある時点、ある条件下でのみの価格であり、為替や生産数量の変化で大きく振れることを考慮する必要がある。また、海外品であれば当然、製造リードタイムが長くなるため、たとえば半年後の不確かな情報で注文を出す必要があるため、作り過ぎによる廃棄/不足による特急高額調達の可能性が増大するし、何よりもトラブルが発生した時の対応工数(海外出張等)は国内産の比ではなくなる。このような想定外のことを考慮した上での導入検討を行っていないため、見えないコストが積み上がっている。
上記事例はいずれもコストの見える化をして、高コストなものに対して手を打ち始めたところまでは良かったのですが、
・低減したコストの受け皿・仕組みの準備不足(=①②)、および
・成果をあせるが故に近視眼的/個別最適思考に走った的外れな活動(=③④)
ということが出来ます。
つまり、自らが打った施策についてそれが実現できたときの成果の刈り取り方を仕組みとして構築しておくこと、また、打った施策によってどれだけの見えないコストが発生するのか?
そのポテンシャルを事前にしっかりと見極める必要があります。
|